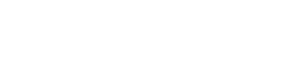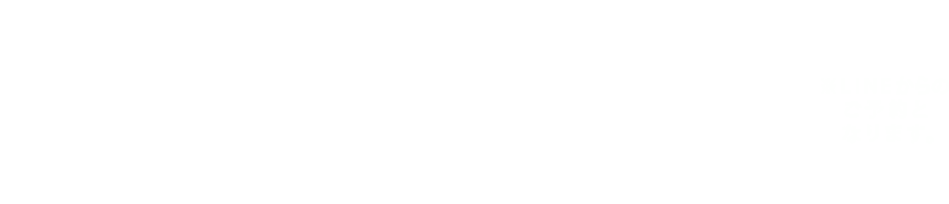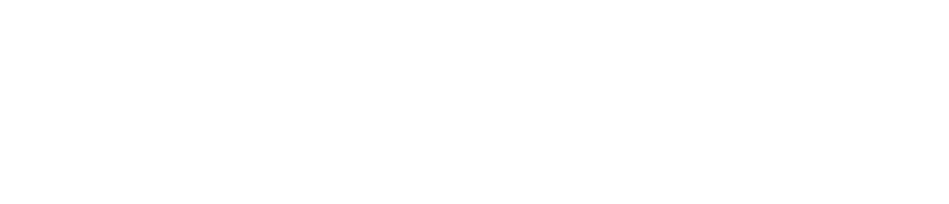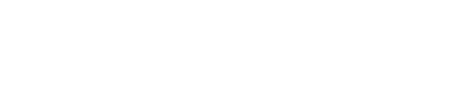自己成長コース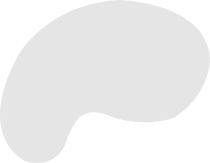
自己肯定感を上げたいと思ったら、
「個性(強み)」を「発見・活かす」ところからスタートしていきましょう。
「もっと自信をもって」と言われることはありませんか?それは周りの評価よりも、自己評価が低いという状況が続いているのかもしれません。
自己肯定感が低いままの状態が長く続くと、努力をしても自分のことを否定し続けたり、マイナス面を見つけては「もっと努力しなくてはいけない…」と自分自身を過度に追い込んでしまいます。
その結果、心が疲れ切ってしまって心の病になってしまうということもあるのです。
「もっと自信をもって」というのは、自分自身のことを見つめなおし、個性(強み)に目を向ける段階に入っていると考えるのが良いのではないでしょうか。
学生の頃は「100点満点」という明確な基準がありました。その100点満点に近づけるために不得意な部分を一生懸命頑張り、
総合点を上げることに必死になっていたと思います。
しかし、社会に出てからは「100点満点」という明確な基準がなくなり、何をしたとしても「もっと出来たのではないか?」「もっと良い方法があったかもしれない」とマイナス面だけを探し、自分自信を追い込んでしまうのです。
自信がある人とない人の違い
自信がある人と自信がない人の違いは「基準をどこに合わせているか」にあると思います。
自信がある人(自己肯定感の高い人)は、自分の個性(強み)に基準を合わせている場合が多く、個性(強み)を伸ばしたり、個性(強み)が活かせる環境を選ぶことができます。その上で「出来た」という成功体験を重ねていくことで自分の個性を再認識し、さらに自信を持つことができます。
一方、自信がない(自己肯定感が低い人)は、学生の頃の経験をベースに“100点満点”を目指している場合が多く、できないことや苦手なこと(弱み)を克服することに取り組んでいきます。できないことや苦手なことを克服することで大きな成果を出す人もいますが、多くの人は無理に苦手克服に取り組み続けることで自分のできないこと・苦手なことに注視してしまい「自分はなんでこんなにできないんだろう…」と、マイナス思考や自己肯定感を下げてしまうケースが多いです。
周りの人たちから「自信をもって」と言われるということは、あなたが今まで取り組んできたこと・頑張ってきたことは認められている状況だといえます。しかし「でも〇〇は出来なかった」「もっと〇〇出来たはず」と、成功体験に対してマイナス面を探そうとする考え方の癖が邪魔をして、その事実を否定している状況なのかもしれません。
このような時に効果的なのが「自己成長コース」です。明日も見方の自己成長コースでは、まずはあなた自身の「強み(個性)」を知るところからスタートしていきます。そして、あなたの強み(個性)を磨き、発揮できる環境が整えることで成功体験を増やし、その成功体験を正しく認識していくためのトレーニングを取り入れていくことで、自己肯定感を高める効果が期待できます。
100点満点を目指すためにはマイナス面に目を向ける必要があったと思いますが、社会には100点満点はありません。100点満点がないということは、150点、200点、300点…とさらなる高得点を目指すことも可能なのです。そのためにはあなたの強みや個性を磨いて、活かしていくことがとても大切なのです。
「もっと自信をもって」
と言われる理由
「もっと自信をもって」と周りの人から言われるということは、自己評価が著しく低く、周りからの評価や賞賛を受け入れられていない状態なのではないでしょうか?
私たちは、学校教育を通して「不得意な部分を良くしていくこと、苦手をなくすこと」に取り組んでいた場合が多く、その考え方が癖になってしまった人もいるでしょう。そして真面目な人ほど改善意識も高くなり、悪かったところや改善点に目を向ける頻度が多くなります。会社での苦手な業務を改善することや、問題なく終えた業務に対しても悪かった点や改善点などマイナス面ばかりに目を向けることに繋がっており、自己肯定感が低くなる原因となっていると考えています。
そして、マイナス面ばかりに意識がいきやすい人は「自分よりもできる人はいる、自分はまだまだだ」とマイナスな言葉を自分自身にかけ続けてしまい、その結果自己肯定感が低くなっている可能性が高いです。まずは、現在の状況を客観視することと、その状況を正しく認識していくことが重要なのです。
しかし、自分自身のことを客観視することは非常に難しいことかもしれません。そこで明日も見方の「自己成長コース」では、現在の状況を正しく認識(客観視)することと同時に、あなたの強みを発掘し、今の環境でどのように活かしていくかを一緒に考え実践していきます。その結果に対しても正しく認識(客観視)させていくことで、少しずつ自信をつけて自己肯定感をあげていきます。
今までのようなマイナス面ばかりを注目する考え方の癖から、プラスの面に注目していくトレーニングや自分の強みを活かしていく方法、考え方を学び習慣化させる必要があります。半年程度トレーニングに取り組んでいくことで、考え方が定着しより良い効果が見込めます。
「調子が上がらない」と悩む
33歳男性の例
私は小さいころから親に認めてほしいという気持ちが強くありました。何かを達成したり良いことがあるといつも親に報告していたのですが、親からは「調子に乗ってはいけない」と言われ続けました。いつしか誰かに褒められても「調子に乗ってはいけない」と瞬時に親の言葉が頭をよぎるようになり、それは社会人になっても続きました。会社で上司から褒められても「調子に乗ってはいけない」と自分で否定し続けていました。
そんな中、自己成長コースのキャリアトランプ®で自分の強みを知れたことは、私にとっては大きな転機となりました。キャリアトランプ®を使って、自分自身で自分のことを深堀していき、今まで気が付かなかった強みを発見することができました。誰かに言われたことは信用できず否定ばかりしてしまうのですが、自分自身で選んだカードだったので自分にも強みがあったんだと初めて受け入れられた気がしました。
キャリアトランプ®で見つけた強みは「小さなことに気付く力」で、今までは自分の欠点だと思っていたのですが、改めて考えると現在の組織でも役に立っていることに気付き仕事に対して少し希望が持てた気がしました。
私は自己成長コースを1年半ほど受けたのですが、最後の最後まで「調子にのってはいけない」と瞬時に否定する癖が抜けませんでした。なかなか改善できず悩んでいた時、カウンセラーさんから「調子に乗ってこなかったんだから、調子は上がっていかないよね」と言われ、はっとしました。
確かに自分自身では調子に乗れないと言いながらも、私は何度も「調子にのってはいけない」と繰り返し自分自身に言い聞かせ調子をあげることを避けていたのです。また「ご両親は、謙虚に色々なことにチャレンジして可能性を高めてほしいという思いから、そのように言っていたのかもしれないね」とも言われ、否定されていたわけではないのかもしれないと思うことができ、気が楽になったことを覚えています。
自分の強みを受け入れることができた今、その強みを活かせる分野で自信を持ち、調子が上がるようにしていくことも良いことなのかなと前向きに考えられるようになりました。
今では「小さなことに気付く力」は誰にも負けない強みであると自負していて、職場での最終チェックなど自分の強みを活かせるようなポジションを担当させてもらうことが増えました。自分の強みを活かすことで職場でも頼りにされていると実感でき、さらに自信を持てるようになってきました。
昔の自分だったら「調子に乗ってはいけない」と考えては成長の機会を逃していたかもしれませんが、自己成長コースを経て「私には強みがある、誰にも負けない」と思えるようになりました。いまだに「調子に乗ってはいけない」という言葉が頭をよぎることはありますが、自分の強みに自信を持つことができるようになったことで、その言葉に惑わされず先に進む勇気が持てるようになっています。
《1回ごとのご相談》
60分 / 6,000円(税込6,600円)
90分 / 8,000円(税込8,800円)
自己成長(自己肯定感をあげる)
コースのご案内
【自己成長コース:知識編】
1日で自己成長に必要な知識を身につけるコースです。自己成長に必要な理論を学びます。
1)考え方の仕組みについて
2)考え方を定着させる方法
3)考え方を変化させる基礎(環境)作りについて
4時間:60,000円
(税込66,000円)
※考え方を変えたい場合は、まず理論を把握して順序よく進めていくことが重要になります。自己成長コース知識編は、思考についての知識と思考を変えていくための土台作りについての知識を学ぶコースとなっています。
【自己成長コース:キャリアトランプ®編】
自己成長コースでは、自分の強みを発掘するためにカード(キャリアトランプ®)を使ってあなた自身のことを掘り下げていきます。
自分のことを知ろうと思っても客観視することが難しい場合がありますが、キャリアトランプ®というカードを使ってゲーム感覚で進めていくため、楽しみながら今まで気づくことが難しかった自分の強みを知ることができます。
①個性(強み)の発見
キャリアトランプ®というカードを使って自分のことを掘り下げていきます。キャリアトランプ®を使うことで自分のことを「言語化」していくことができ、客観的に見るきっかけとなります。
②個性(強み)の認識
あなたの思考の癖がマイナス面を捉えやすいものの場合、良い体験をしてもマイナス面ばかりを注目してしまうことが増えます。あなたの個性(強み)に関しても弱点や弱みとして捉えてしまっていることで、強みを活かせていない場合が多くあります。
そこで自己成長(自己肯定感をあげる)コースでは、現在の体験を客観的に見つめ直すところからスタートしていきます。そして客観的に見つめ直した体験の中で、自分の個性が活かされている状況をリストアップしていきます。そのリストアップしたことを一緒にプラスの側面から見直し、繰り返し行うことで自分の強みを少しずつ認識していくことに繋がります。
③個性(強み)を活かす環境
「長所と短所は紙一重」と言われることがありますが、そのほとんどは環境が影響しています。自分に合った環境で過ごしている場合は個性は強みとして発揮されますが、一方、自分に合わない環境では、個性が弱みとして受け取られてしまうことがあります。合わない環境で頑張り続けたことで弱みとして認識してしまうことが増え、結果的に自己肯定感が低くなってしまうことが多いのです。
しかし、成長するためには頑張ることや厳しさも必要であることは間違いありません。そこで重要なのが自分に合った環境かどうか、厳しさがあるかどうかということです。
苦手を改善することが成長だと考えている場合は、自分に合わない部分は改善できる要素ととらえ、合わない環境にも身を置き続けてしまうことがあります。しかし、その環境では成長は見込めない場合が多いのです。
あなたの個性を活かしていくためには、自分の中でどのように個性(強み)を活かすことができる環境を整えていくのかということがポイントになります。もし、現在の環境で自分の強みを活かすことができる場合は、そのお仕事で強みを活かす方法を一緒に考えていきましょう。
時間をかけて①~③を積みあげていくことで、自己肯定感は少しずつ変化していきます。しかし、思考を変えるということにもなりますので、ある程度の時間と習慣化が必要となります。焦りを感じてしまうところではありますが、地道に繰り返して取り組んでいくことが自己肯定感をあげていく上でとても重要なポイントになります。明日も味方の「自己成長(自己肯定感をあげる)コース」では、あなたの自己肯定感を上げていくためのお手伝いをさせていただきます。
90分 / 10,000円
(税込11,000円)
※自己成長コース:キャリアトランプ®編は、考えることが多くなります。そのため、脳疲労を感じている方は一度「相談・カウンセリング」をご検討ください。